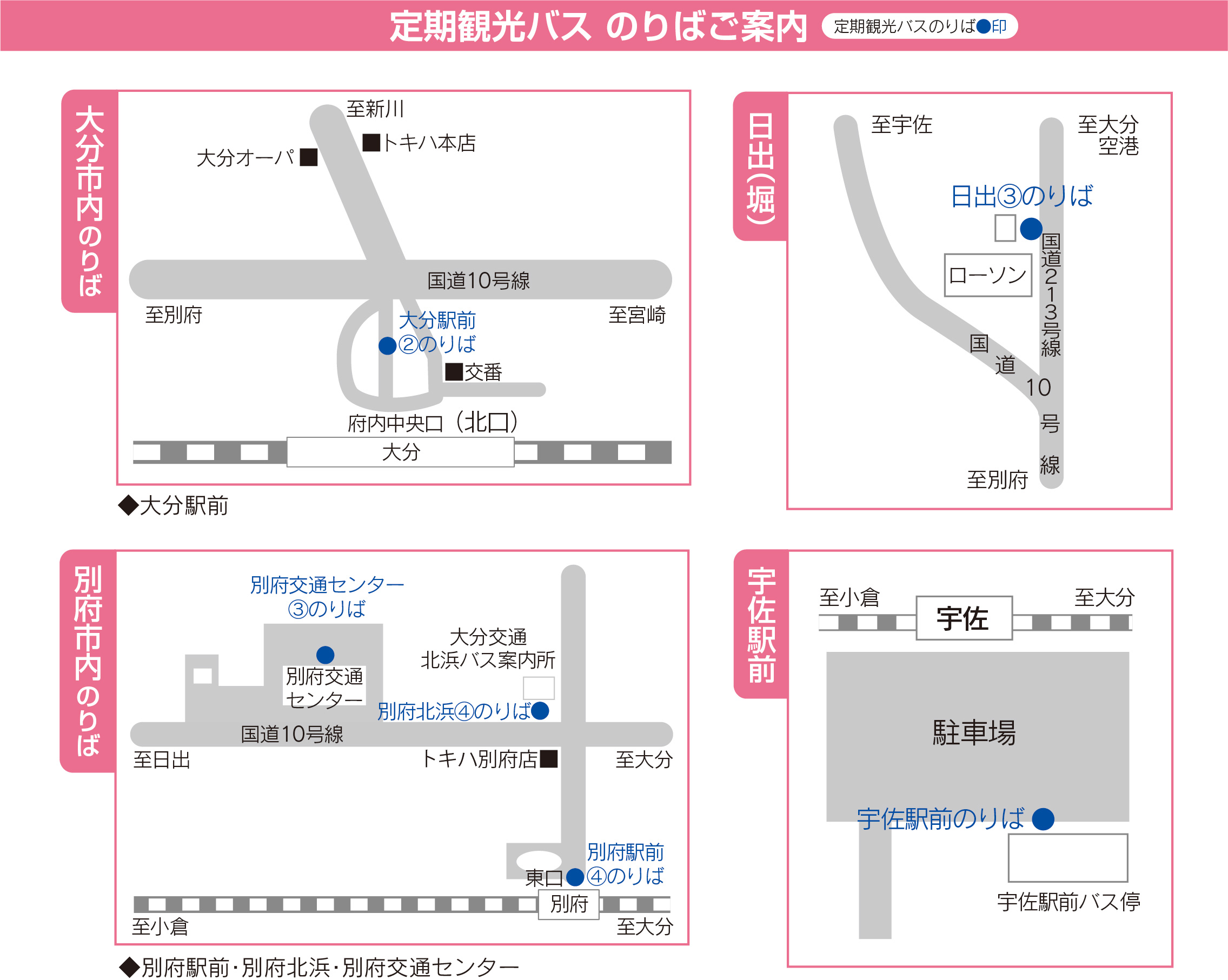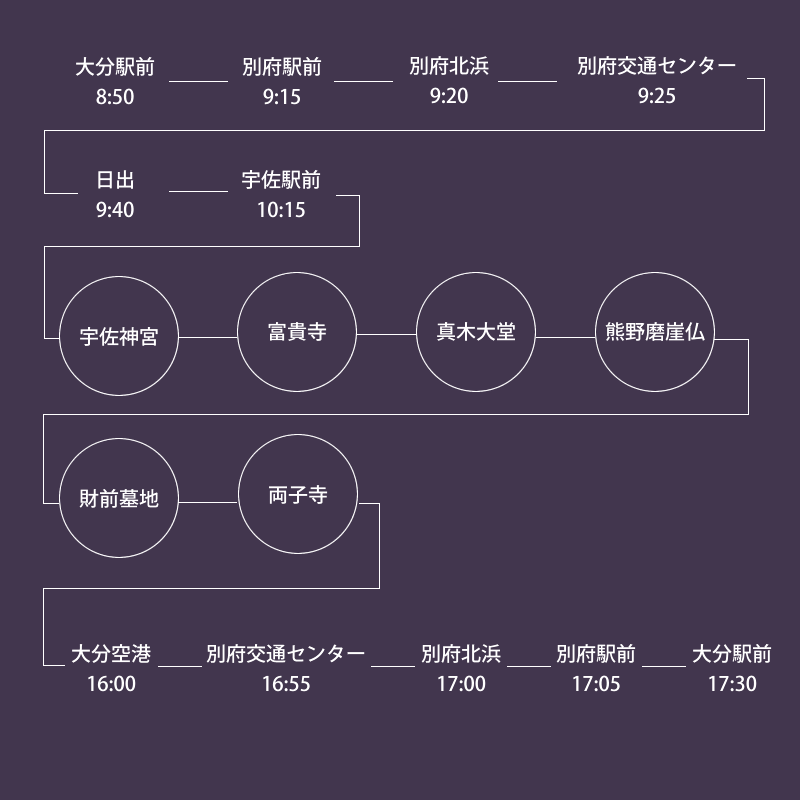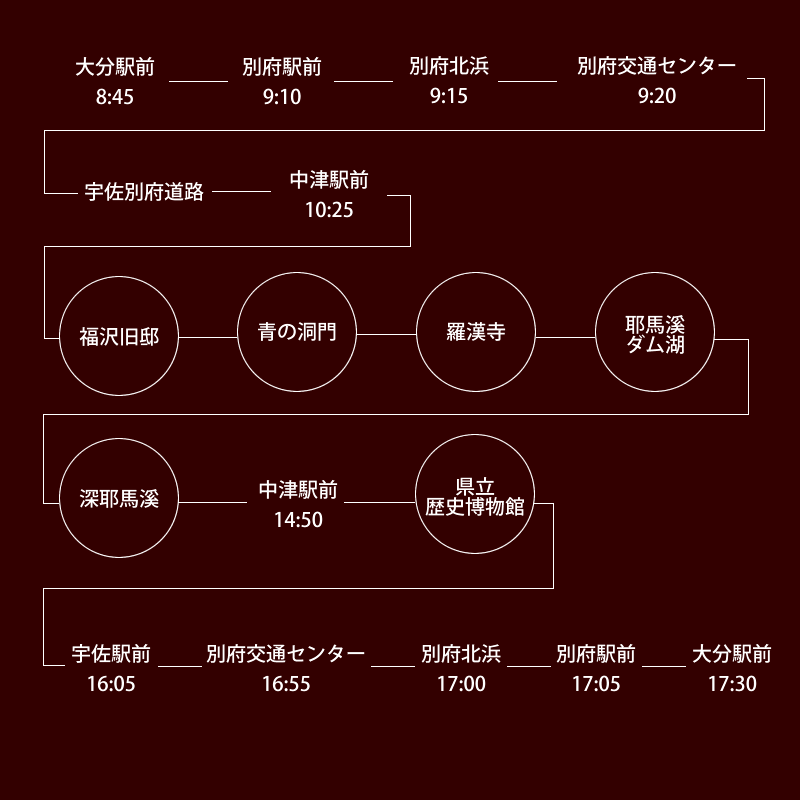国東半島史跡巡り
四季折々の仏の里を満喫しませんか?
-

宇佐神宮
うさじんぐう
聖武天皇が神亀二年(七二五年)に創建された。全国4万の八幡宮の総本社で、奈良時代から朝廷の崇敬厚く、往時、国東半島の六郷満山を形成、統括し、12世紀頃には九州一円の荘園領主であった。社殿は古い神社本殿の一形式を伝え、「八幡造」と呼ばれ国宝に指定されている。
-

富貴寺
ふきじ
現存する九州最古の木造建築である大堂は国宝。仁聞の開基といわれる。現在の建物は平安時代後期のもので一本の榧の木で建立したと伝えられ、建築、壁画、彫刻の三者を備え、境内には国東塔、笠塔婆等の貴重な石造美術品が多い。
-

真木大堂
まきおおどう
六郷満山65ヶ寺の中、本山本寺として最大の寺院であった馬城山伝乗寺のことである。現存する九体の仏像は何れも国指定重要文化財で全霊をつくして作者の魂がこもっている。仏像の作風からみて平安時代の作である。
-

熊野磨崖仏
くまのまがいぶつ
胎蔵寺から250m登った所にある巨大な不動明王(8m)と、大日如来(6.8m)の磨崖仏で、豊後磨崖仏の代表的な物である。藤原末期の作と云われ、両像とも厚肉彫りで国指定重要文化財及び史跡である。
※12/8~3月末(予定)の期間中、一部改修工事の為、見えづらい所がございます。
予めご了承ください。 -

財前墓地
ざいぜんぼち
墓地一帯に100余りもの国東塔群が散在しており、中には財前美濃守の墓と伝えられる宝塔もあります。
-

両子寺
ふたごじ
国東半島の最高峰両子山(標高721m)の中腹に在り、仁聞開基の寺伝をもつ六郷満山中山寺の古刹である。国東半島最大の優れた仁王像をはじめ、綜合門、本堂、護摩堂、奥の院等往時の寺院形態を良く伝えるたたずまいである。